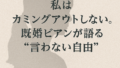「私はレズビアンなのかもしれない」と思った最初の瞬間
高校生のとき、私は女子高に入学して、演劇をしていました。毎日が新しくて、舞台の光と汗と笑い声に満ちた日々。その中で、同級生のひとりのことを、気づけば目で追っている自分に気づきました。
声の響き方、笑ったときの横顔、舞台袖で台本を抱える姿。そのすべてが、胸の奥で静かに灯りをともすようでした。
けれど、その子を好きだったのは私だけではありませんでした。尊敬していた先輩も、同じ人を想っていたのです。そのことを知ったとき、私はそっと自分の気持ちを引き出しにしまいました。「先輩と同じ人を好きになるなんて」と思いながら、あきらめるという選択をしました。
不思議なことに、そのときの私は「同性を好きになった」という意識を、ほとんど持っていませんでした。女子高では、女子同士の恋愛は特別なものではなく、どこか「普通」にそこにある空気の一部だったからです。
だからこそ、「レズビアン」という言葉は、その頃の私の辞書にはまだ存在していませんでした。ただ、胸の奥で静かに灯る「好き」という感情だけが、確かにそこにありました。
“好きになる相手”が男性だった時期もあった
高校を卒業して社会に出ると、周りの空気はがらりと変わりました。「いつか男性と出会って結婚する」という前提が、当たり前のようにそこにありました。
その影響もあってか、私はどこかで「出会わなければいけない男性がいる」と信じるようになりました。まるで、どこかにいる“運命の誰か”を探すように、好意を向けてくれる男性たちと、次々に付き合っていきました。
その中で、魂の双子のような存在――いわゆる「パパ彼」と出会います。彼は恋人というより、人生の伴走者のような存在でした。私の中にある男性性や女性性の揺らぎを、言葉にしなくても、どこかで理解してくれているような、不思議な安心感がありました。
そして、ネットの海の中で、私は「出会わなければならなかった男性」と巡り合います。のちに夫となる人です。
彼との出会いは、いわゆる恋愛というよりも、「魂の縁」に近いものでした。私の中のレズビアン性を否定するものではなく、むしろ、私という存在の複雑さを、そのまま受け止めてくれるような関係でした。
私の中の“レズビアン性”はどこから来て、どこへ向かうのか
振り返ってみると、私の中のレズビアン性は、「固定されたラベル」ではありませんでした。人生の節目ごとに、少しずつ形を変えながら、それでも途切れることなく流れ続けてきた、ひとつの“流れ”のようなものです。
- 女子高で、初めて同性を好きになったあの瞬間
- 社会の期待に合わせて、男性と付き合っていた時期
- 魂の双子のようなパパ彼との出会
- そして、夫という「縁の人」との結婚
- そして既婚ビアンという言葉を生んでからの「僕」
そのどれもが矛盾ではなく、「私」という物語の一部です。
変わらないものは、誰かを深く愛する心と、自分の中にある静かな中心。
変わっていくものは、社会との距離感や、自分の名乗り方、そして「生きやすさ」の基準。
レズビアン性は、私の中で静かに息をしながら、これからも形を変え、流れ続けていくのだと思います。
それは、ひとつの答えに閉じ込めるためのものではなく、「私という物語」をこれからも紡いでいくための、大切な一部なのだと、今は静かに感じています。